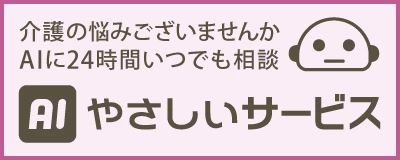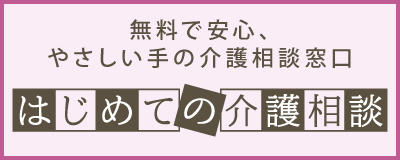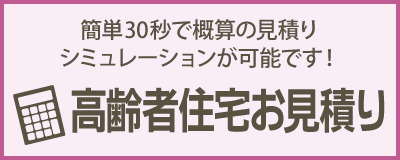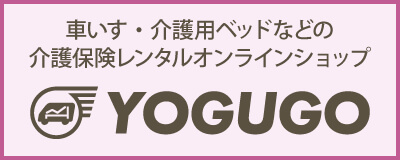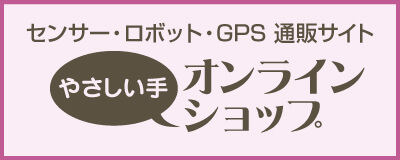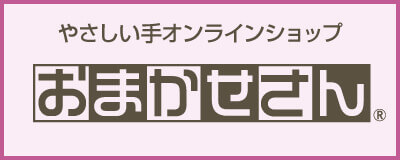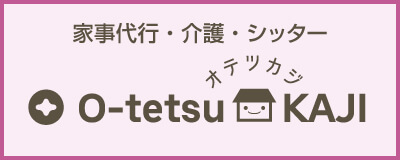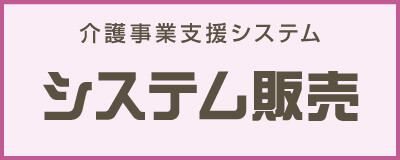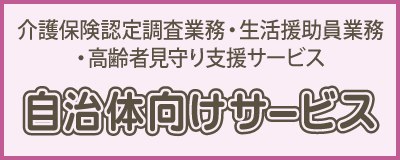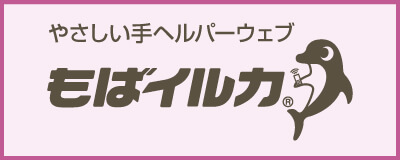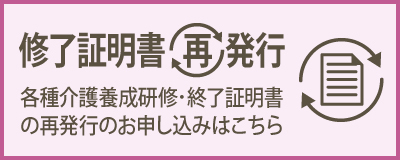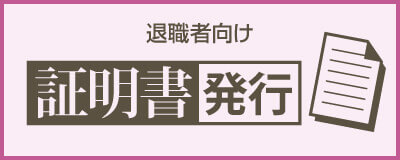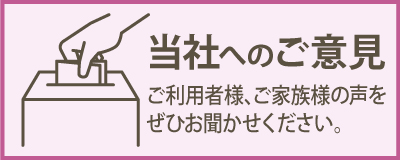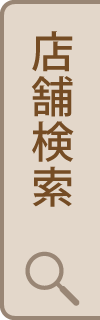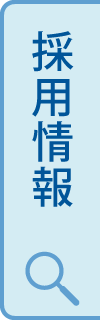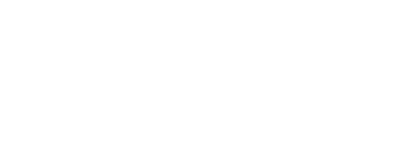本事例は余命数日と言われた利用者様を5ヶ月間、 週2回の訪問看護を通じて在宅看取りを実現した成功例です。 主治医と連携し、次女様を主介護者として支援しました。
経過
初期(10月中旬) 総合病院退院後、訪問看護開始。食欲良好で自力での体位交換が可能でした。両膝に熱感があり、右膝に疼痛と褥瘡がみられました。退院時処方は主治医と相談し調整しました。 中期(11月〜12月) 食欲維持、会話も活発で認知機能も良好でした。テレビ視聴や数字つなぎパズルを楽しまれていました。夜間の覚醒が多く次女様の介護負担が大きかったため、エンレスト追加で血圧コントロールを改善しました。 終末期(1月〜3月) 1月中旬より全身状態が低下し、食事量減少、意識レベルの波動がみられました。両肺に水泡音が出現し、全身浮腫が増強。3月1日午前5時に永眠されました。看護の成果
症状管理の成果 エンレスト追加後、血圧は140-160台から120-130台へ安定。SpO2は93-97%を維持し、体温も36.5-37.2度で安定しました。エアマット導入や定期的な体位変換指導により褥瘡予防を実現。疼痛部位に応じた湿布貼付やカロナール適切使用の指導により、疼痛コントロールも達成しました。 ADL維持と生活の質向上 初期は5分程度だった端座位が中期には20分程度まで延長。足踏み運動や下肢ROM運動を継続し、本人の体調に合わせた運動量調整を行いました。本人希望に応じた洗髪実施やドライシャンプーの活用、全身清拭による快適性確保、口腔ケアの継続により清潔ケアを充実させました。 家族支援の成果 オムツ交換方法や体位変換の技術、食事介助方法、観察ポイントの説明など介護技術を指導。次女の介護負担への傾聴や介護の労をねぎらう声かけ、24時間対応による安心感の提供により精神的サポートを行いました。状態変化の段階的な説明や予測される経過の説明により、看取りまでの支援を実現しました。 多職種連携の成果 主治医への状態変化の適切な報告や処方調整の提案、往診時期の調整、看取り期の連携を行いました。ケアマネジャーとはサービス調整や福祉用具の導入時期検討、家族支援の情報共有を行いました。これらの成果により、本人の望む在宅生活を可能な限り維持し、安らかな最期を迎えることができました。また、家族の満足度も高く、在宅看取りを実現できた事例となりました。