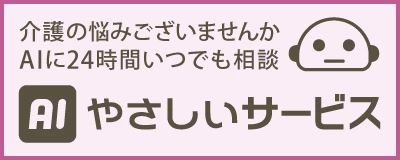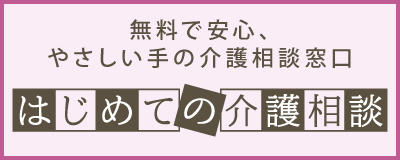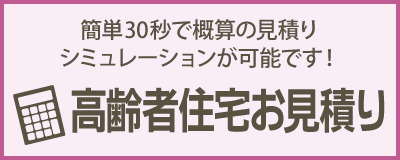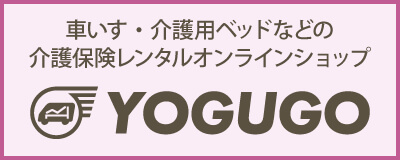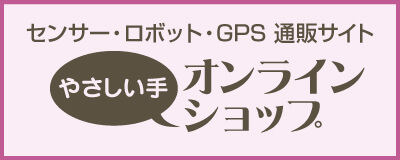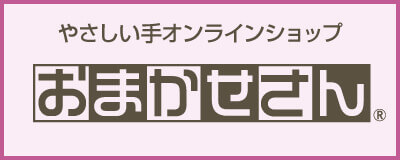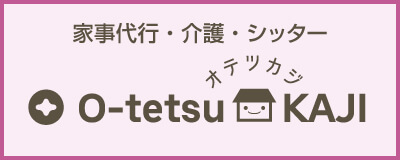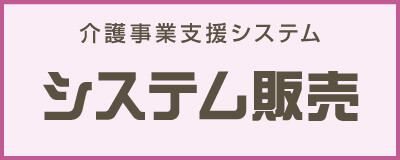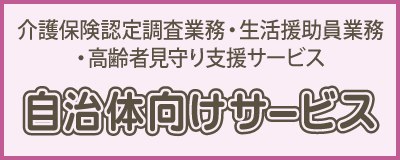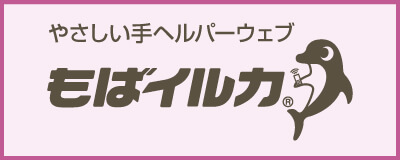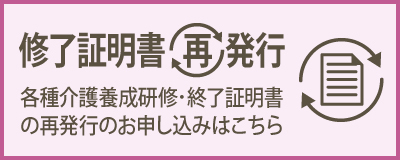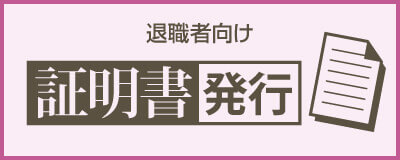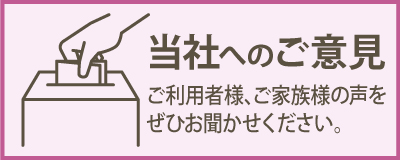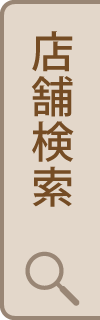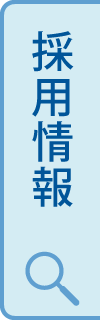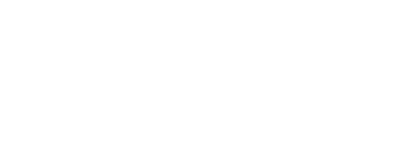2025年10月9日(木) 開催 運営推進会議 議事録
2025.10.15
令和7年 第5回 運営推進会議議事録
1、 日時: 令和 7年 10月 9日(木) 14:00~14:30
2、 場所: 看多機かえりえ楠
3、出席者
丹羽 様(利用者様ご家族)
伊藤様(株式会社トーカイ)
落合様(北区西部いきいき支援センター分室)
渋谷 友紀(管理者)
後藤 千秋(計画作成者)
千田 昌宏(介護リーダー)
4、 報告
① 参加者様紹介
② サービス実施報告
●ご利用者数
7 月:16名 (緊急短期利用 3名)
8 月:20名 (緊急短期利用 2名)
9 月:20名 (緊急短期利用 0名)
●要介護度
要介護度1…4名 要介護度2…3名 要介護度3…6名
要介護度4…3名 要介護度5…4名
平均介護度:3
●依頼先
【問い合わせのあった機関】
▪総合上飯田第一病院(病院)▪名城病院(病院)▪北病院(病院)・
▪西部医療センター(病院)▪AOI病院(病院)▪名鉄病院(病院)・
▪名古屋医療センター(病院)▪北医療生協居宅▪愛生居宅▪やさしい手楠居宅
●医療処置
内服管理、嚥下機能評価と食事形態の調整、摘便・浣腸、在宅酸素管理、自己導尿の支援、
膀胱留置カテーテル管理、褥瘡処置、吸引、点滴、胃ろう、血糖測定、帰宅に伴う手技習得の指導
③ インシデント報告
〇個室内での転倒事故
夜間帯居室から出てこられた際にドアを開けてすぐに膝が抜け転倒。
問題点
⑴ ご自身で動く可能性がありセンサーマットをセットしていたが間に合わず。センサーの位置が悪くセンサーの反応が遅れていた。
⑵ 日中眠そうにされていることが多いため夜間睡眠が浅く、夜間帯扉が開いているとスタッフの動きなど気になるようで、起きてこられることがあり夜間帯扉をしめていた、そのためセンサーを使用していた。今回も個室扉は閉っており立ち上がろうとしたことに気が付けなかった。
是正
⑴ センサーの位置修正し、起居時にセンサーが反応するように調整いたしました。
⑵ 昼夜逆転を防ぐため日中の活動量を増やし、できるだけ昼間は起きてもらうように声かけやアクトへの参加を促すようにスタッフ間で連携するように体制を変更いたしました。
④ アクティビティ・イベント紹介
園芸、オクラやトマトが収穫できました。午後など一緒に水やりを行ってもらっています。
→収穫したオクラは茹でて少量ずつ分けて利用者様と一緒に食べました。トマトは洗って切り分けて食べてもらいました。
10月12日(日) 楠地区のお祭りに参加予定
→当日参加可能な利用者様をお連れし参加する予定です。
⑤ 寒暖差疲労・アレルギーについて
〇近年季節間の寒暖差が大きくなってきています。
気温差が7℃以上になると症状が現れることが多くなります。寒暖差により自律神経が乱れやすくなり、疲労感、倦怠感、めまい、頭痛などの症状が出ます。特に、春や秋の季節の変わり目は、寒暖差疲労を引き起こしやすい時期です。
〇寒暖差アレルギーとは正式には「血管運動性鼻炎」と呼ばれ、アレルギー性物質が関与しない、温度差によって鼻の粘膜の知覚神経が刺激されることでくしゃみや鼻水が起き、鼻の粘膜の血管が拡張することで鼻水・鼻づまりといったアレルギー症状が出る状態を指します。
〇各年ごとの10月の気温・特徴
各地方都市ごとの10月の気温には顕著な違いがあります。大阪では蒸し暑さが残る日があり、名古屋は朝晩の冷え込みが強まり始めます。福岡では秋晴れの日が多い一方で、予想外の暑さを感じることもあります。北海道ではすでにストーブが必要なほど冷える日もあり、10月は冬の入り口です。
〇寒暖差疲労の予防方法
・適度な運動
運動を習慣づけることで、自律神経のバランスを保つことができます。
15分~30分程度の軽い有酸素運動やウォーキング、ストレッチが効果的です。
デスクワークが多い方は1時間に1回程度首や肩のストレッチすることも効果的です。
・十分な睡眠
自律神経を整えるには、十分な睡眠時間を確保することが大切です。また、質の高い睡眠をとることで、体の回復力を高めます。睡眠の質を高めるためには、就寝前の飲酒やカフェインの摂取、スマホ・テレビの利用・視聴を控えましょう。
・温度差を小さくする
体温調整がしやすい服装で、朝晩や日中の気温差に対応できるよう、重ね着や簡単に脱ぎ着できる服装を選ぶと寒暖差を小さくでき体への負担を軽減できます。ニュース等で天気予報を確認し、最低・最高気温、天気状況の確認をすると、より適した服装を選ぶことができます。
●次回のご予定
看多機かえりえ楠 令和7年度第6回運営推進会議
12月中旬頃 14時からを予定